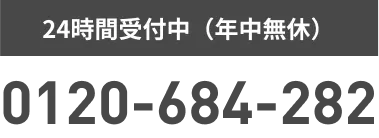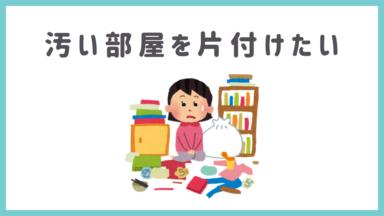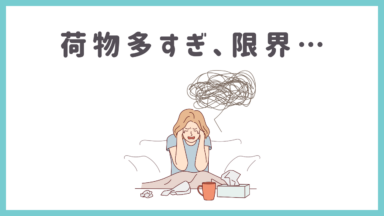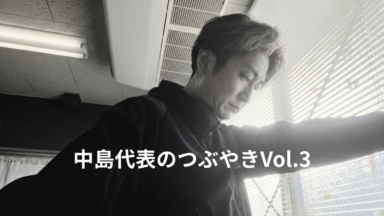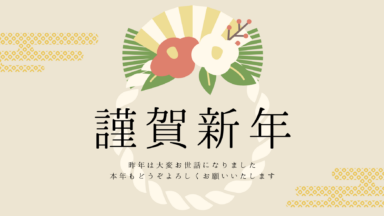スタッフブログ
- スタッフブログ
- 中学生の子供の部屋が汚い!自主的に片付ける習慣作りと収納のコツ
中学生の子供の部屋が汚い!自主的に片付ける習慣作りと収納のコツ

「中学生の子供の部屋が散らかりっぱなし」
「片付けで親子喧嘩がしょっちゅう起こってしまう」
子供が中学生になれば個人で部屋をもつことも多くなるので、このように悩む人もいるのではないでしょうか。
今回は中学生の部屋が汚い理由、子供が自主的に片付ける習慣作りのコツや、自分でできる収納のコツなどを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
中学生の部屋が汚い理由
子供の部屋が汚いことは決して子供本人も望んでいる訳ではありません。
中学生の部屋が汚くなるのにはいくつか理由があるのをご存じでしょうか。
ぜひ、子供のライフスタイルと照らしあわせながら確認してみてください。
学用品など物の管理が大変になる
中学校は小学校と比べて学習する科目数が増えるため、教科書以外に辞書や参考書、タブレットなど大幅に学用品が増えます。
また、テストも頻繁に行うためお便り以外にテスト用紙や問題集などのプリントもかさみます。
学校に限らず塾に通えばさらに教材やプリントもあるため、膨大な物を分かりやすく管理するのは大人でも大変な作業です。
保育園や小学校からの物がしまいっぱなし
子供部屋に保育園や小学校からの物がしまいっぱなしなのも、部屋が汚くなる理由のひとつです。
ただでさえ中学校で学用品が増えて管理が大変なのに、使わない過去の物は片付けを妨げる要因になりかねません。
勉強や部活などで時間がない
中学生になると高校受験に向けた勉強や塾、部活などで朝から夜まで大忙しです。
家にいても学校や塾の宿題や予習復習でくつろぐ時間もままならないほどです。
毎日「やらなければいけない」ことに全力なので、ご飯を食べて眠くなれば散らかったままでもいいやと片付けを後回しにしがちになります。
学用品以外の物が増える
中学生になって増えるのは学用品だけではありません。
部活なら運動部系でも文化部系でもユニフォームや道具など活動に応じた物が必要になります。
また、小学生の頃よりも遊ぶジャンルや行動範囲が広がるので、ゲームや漫画、本などを際限なく置けば部屋はどんどん手狭になり、散らかりやすくなるので注意が必要です。
部屋が汚くて起こるデメリット
部屋が散らかっていると、勉強やスポーツに打ち込む時間を探し物にあてがわなければいけないので非効率です。
探し物をすれば学校や部活などの約束の時間に追われて焦ったり、物が見つからない不安でイライラしてストレスがかかります。
精神的にも穏やかでいられないため勉強にも集中できず、親にやつ当たりする場合もあるでしょう。
また、部屋が汚いと掃除も不十分になりダニや埃が溜まりハウスダストなどの健康面のリスクも出てきます。
さらに、中学生は多感な時期なので部屋が汚いことで友達にからかわれたり避けられる場合もあります。
部屋が汚いというだけで、じつは勉強やスポーツ、友達との交流や健康などいろんな場面で影響を及ぼす可能性があるのです。
中学生が自主的に片付ける習慣作りのコツ
中学生の部屋を親が勝手に片付けるのはトラブルの元になりかねません。
ここでは、中学生が自主的に片付ける習慣作りのコツを5つ紹介します。
毎日忙しい中学生でも、コツを理解すれば散らかりにくくなるはずです。
ぜひ、試してみてください。
片付ける日を決める
中学生は日々忙しいので「時間が空いたら片付ける」にしているといつまでも片付けられず部屋は散らかっていきます。
そうならないためにも、時間割のように片付ける日を決めることが大切です。
毎日寝る前に5分、ゴミの日前日に片付けるなど子供にストレスがかからない設定でチャレンジしてみましょう。
「これは続けられないかも」と思えば片付ける日を再設定できるのもメリットです。
目的は片付けを継続させることです。
一気に部屋を綺麗にするのではなく、続けられるハードルを見つけて生活の中に取り入れてみましょう。
片付ける場所を決める
片付ける場所を決めるのも習慣作りには欠かせません。
テスト勉強で範囲を決めずに取りかかろうとしても、どこから手をつけたらいいか迷うのと同じです。
今日は勉強机の上、次の日はクローゼットなど場所を決めてから始めましょう。
場所を決めることで集中できますし、片付いた変化も目に見えて分かるので達成感も得られてモチベーションにつながります。
どこから片付けるか迷う場合は、普段よく使う場所から始めるのがオススメです。
また、場所に限らずプリント類や服などカテゴリーで分けるのも片付けの時短につながります。
使わない物は捨てる
部屋が汚くなる原因のひとつは物が多すぎることです。
小学生の頃の物や使い終わったプリントなど、部屋にある使わない物を捨てるだけでもスッキリするはずです。
捨てるか残すかの判断は物をひとつずつ確認するしかありませんが、片付ける日や場所を決めて少しずつ見直していくと、自分にとって必要な物が分かるようになります。
一時置き場を活用する
使わない物を捨てる際に、迷う物が出たら保留用として期間を設けて分けておきましょう。
分けておくと本当に必要な物と混ざらないので、再度見直す時もスムーズです。
他にも、洗濯に出すほどではない服なども一時置き場を作っておくと散らかりにくくなるだけでなく、洗濯に出す服が分かるなど次の作業の時短にもつながります。
収納を簡単にする
部屋を散らかさないためには収納を簡単にすることが重要です。
物を使う時は収納場所から取り出しにくくても取り出しますが、しまう時は面倒になり出しっぱなしになる恐れがあります。
そうならないためにも、収納を簡単にすると習慣につながりやすくなるはずです。
ハンガーに引っ掛けるだけ、箱に入れるだけ、棚に置くだけなど楽にしまえる仕組みにすることで収納の面倒をなくしてみましょう。
また、収納の場所も子供の体にストレスがかからない高さや奥行きを考慮すると片付けはとても簡単だと気付けるはずです。
中学生が自分でできる収納のコツ
ここでは、中学生が自分でできる収納のコツを紹介します。
最近はホームセンター以外に100円ショップでも収納グッズは揃えられます。
工夫して使い勝手のいい収納スペースをぜひ作ってみてください。
制服、私服、部活のユニフォームなど
ハンガーに掛ける収納なら収納も簡単で、どこに何があるかもすぐ分かります。
全ての服を吊るすスペースがない場合は、よく着る服だけ厳選したりハンガーラックを設置してみるのがオススメです。
畳む手間が減るので片付けの負担も少なくなります。
また、ハンガーラックの近くに一時置きのスペースを設置しておけば、洗濯にまわさない服などの仕分けもできるので片付けの効率アップにつながります。
帽子、ネクタイ、ベルトなど
ハンガーに掛けにくい帽子、ネクタイ、ベルトなどは突っ張り棒にS字フックや有孔ボードにフックを組み合わせて引っ掛ける収納がオススメです。
物の形も崩れにくく、収納の位置も自分のしまいやすいように並べ替えられる自由度の高さがメリットです。
文房具類
文房具類は物の種類も多いので何をどれくらいの頻度で使っているかが収納のポイントになります。
ペンでもよく使う物だけ筆箱やトレー、ペン立てですぐ使えるように収納して、ストック分は引き出しに仕切り付きトレーにしまえば机も散らからず在庫管理も簡単です。
消しゴムやクリップ、付箋など細々した物も同様に引き出しの中を仕切り付きトレーを活用して収納するとごちゃつきません。
他にも中身が見えるファスナー付きのケースで収納するのもそのまま持ち運べるのでオススメです。
教科書、ノート、参考書、プリントなどの紙類
教科書など紙類は重ねると下の物が何か分からなくなり出しにくくなるので立てて収納しましょう。
教科ごとや塾関係など自分が分かりやすい項目別でファイルボックスやファイルスタンド、ブックエンドで仕切れば放り込むだけなので簡単です。
深さのある引き出しに収納したい時もファイルスタンドやブックエンドで立てる収納にすると省スペースで収まります。
ただし、決めた項目に他の紙類が混ざらないように注意しましょう。
ラベリングで物の定位置を決めておくと他の紙類が混ざるのを回避できるほか、探し物の軽減や忘れ物防止にもつながります。
ゲーム、漫画、DVD、スポーツ用品など
アクリル仕切りスタンドはタブレットやゲーム機を収納したり、箱やカゴはコントローラーをしまうのにピッタリです。
さらに持ち手付きの箱なら持ち運びもできますし、箱の穴から配線もできるので設置と片付けの手間が省けます。
ゲームソフトは透明や半透明のケースなら中身も分かりやすく、コードはポーチにざっくり収納するのもいいでしょう。
漫画やDVDも本棚やウォールラックに立てたり、箱なら背表紙が見えるようにしまうと分かりやすくなります。
楽器やスポーツ用品など箱などにしまえない物はディスプレイとして見せる収納でお気に入りのコーナーをつくってみましょう。
自然と物の定位置も決まるので片付けも楽チンになるはずです。
収納用品を使うときに注意すること
いくら便利な収納グッズでも実際に物を出し入れしてみなければ使い勝手の良さは分かりません。
失敗を最小限にするためにも、まずは試しに1個か2個買って検討してみましょう。
その際、収納スペースのサイズを記録しておくとサイズ違いを防げます。
また、ロングセラー商品を選んでおくと廃盤の心配もなく買い足せます。
大切なのは実際子供に試してもらうことです。
本人が面倒と感じたら、どこに問題があるのか確認することが収納用品の失敗を減らす一番の方法です。
まとめ
中学生は勉強や運動、遊びなどで目まぐるしい日々です。
充実した生活を送るためにも片付けは欠かせませんが、完璧を目指す必要はありません。
勉強などほかのことと同じように、できることからコツコツ取り組んでみましょう。
時には失敗する場合もありますが、親子で焦らず片付けに取り組めば、物を選ぶ判断力や”こんな部屋にしたい”という子供の意志が芽生えるはずです。